第5章 中和
非正視矯正の野郎をやっつける方法はいくつかあります:私たちはすでにそのうちの1つである、遠点矯正をすでに考えました。しかし、私は新しい課題である、“中和”を導入するために矯正のもう1つの概念を詳説したいと思います。
全ての非正視には屈折力と軸長の不釣合いがあります。後者は容易に変更できませんので、私たちは屈折力を扱うことに身を委ねなければなりません。私たちがやりたいことはどんな軸長に対しても“適切な”屈折力の目を対応させることです―ジオプター度数が弱過ぎる(遠視)目にはジオプター度数を加え、強過ぎる目(近視)にはジオプター度数を(マイナスレンズを加えて)減らします。
もしプラスレンズに直接くっつけてマイナスレンズを置けば、2つの屈折力は代数的に加わります。両方が同じ屈折力で符号が反対の時、それらはお互いに中和し、合成した屈折力はなくなります。私たちは目でも同じことができます。しかし、その全体の屈折力ではなく屈折異常だけを“中和”するのです。5Dの近視眼は5Dだけ強すぎますので、これは−5Dのレンズで中和されます。このレンズは、しかしながら、目の前面に接触していなければなりません。この同じ概念は、角膜にくっつけたプラスレンズの形でジオプター度数を供給しなければならない遠視の“弱い”目に当てはまります。ではなぜ私が矯正レンズと前部屈折面との接触を強調するのでしょう?
中和は2つのレンズ間のジオプター度数を“釣り合わせて”、無焦点システムにするのです。つまり、入射光線の光の広がり(vergence)がゼロであれば、レンズシステムでは射出(像)光線もゼロの光の広がり(vergence)になるでしょう。レンズがくっついていればマイナスレンズは等しい屈折力のプラスレンズで正確に中和されます。
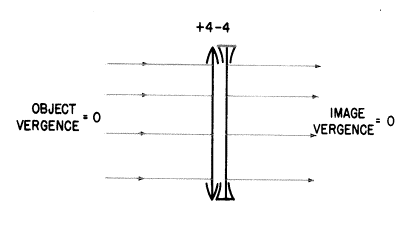
2つのレンズを分離してまだ−4Dのレンズを中和したい時、無焦点システムにするためにはプラスレンズのジオプター度数を小さくしなくてはならないでしょう。“中和するレンズ”にはどれだけのプラスが必要なのかを見てみましょう。−4Dレンズの像の光の広がり(image vergence)がゼロになるためには、物体空間にある光線をその第1焦点Fに向けなければなりません。しかし、マイナスレンズのFはレンズの右にあります。ゆえに、物体空間の光線はそれらを平行光線束で射出させるには、Fに向かって収束していなければなりません。
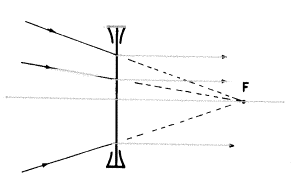
その収束光線を創出するにはプラスレンズが必要です。このレンズは平行な入射光線を捕らえ、その第2焦点F’に向かってそれらを収束できます。だから、もしこのF’がマイナスレンズのFと一緒になれば、“中和された”無焦点システムのための条件は満たされるでしょう―最初の物体の光の広がり(vergence)はゼロで、最終的な像の光の広がり(vergence)もゼロになります。
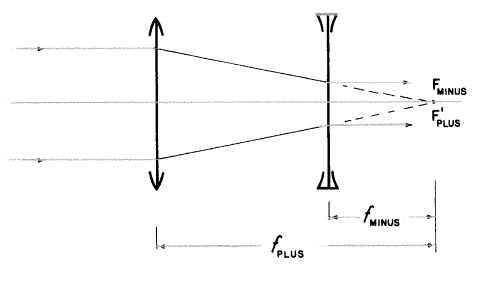
プラスレンズでマイナスレンズを中和できたことは今明らかです。レンズがくっついている時はプラスレンズの第2焦点距離f’はマイナスレンズの第1焦点距離fと同じ長さでしょう―ゆえに、両方は同じ屈折力です。しかし、2つのレンズの間に空間があって焦点を一致させようとするのであれば―中和のための条件―、プラスレンズのf’がもっと長い焦点距離にならなければなりません。レンズの間の距離が大きくなれば、プラスレンズのf’は長くならなければならず、ゆえにそのプラスの屈折力は弱くなります。だから、中和が起こるためには、プラスレンズの屈折力はマイナスレンズの屈折力にいつも等しいか(レンズがくっついている時)、それよりも小さい(離れている時)ということを私たちは今分かったところです。
私たちは“手持ちの”プラスとマイナスレンズについて話していましたが、“目の屈折異常”と“矯正レンズ”についても同様の原理が成り立ちます。つまり、私たちが屈折異常を“中和”させようとする時です。遠視眼はその軸長には小さ過ぎる屈折力を持っていて、目の中に小さい余分なマイナスレンズが“挿入”されたように考えることができます。それはプラス矯正レンズによって矯正(中和)され、もしそれが目の中の“マイナス”レンズにより近付けばその屈折力はより大きくならなければなりません。もし矯正レンズが屈折異常の目から離れて置かれたなら、“矯正”レンズは必然的にプラスの屈折力が減少しなければなりません。(これは遠点と矯正レンズを扱う時に私が作った同一点を見るもう1つの方法です!)
だから、“適切な”矯正レンズの屈折力は変化することができ、それでもなお“矯正する”ことを2つの異なる方法で私は強調したのです。今まで私は矯正レンズの度数を変化させる時何に患者が気付いているのかという問題を避けていました。“中和された”無焦点システム(ガリレイ式光学システムとも呼ばれます)を詳細に調べることでそのような屈折力の操作の間に何が起こっているのかを調べてみましょう。