第4節 不等像視
患者が両眼で見た時の像の大きさに違いを知覚したら、何が原因であるかにかかわらず、その欠点は不等像視とされます。この慢性病の前兆や兆候は他の臨床用教科書に詳しく議論されています。5%以下の大きさの差は兆候を生じることができるといって十分です。臨床的には患者が知覚する大きさの違いは不等像視計(eikonometer)と呼ばれる道具で測られます。
この差を補償するレンズは研磨可能であり、“等像”レンズと呼ばれます。これらは実は部品の間がとても狭い(単位はミリメートル)間隔になっている、小型のガリレイ式拡大鏡(もしくは縮小鏡)です―しかし、この間隔は望ましい像の大きさになるような数パーセントの変化を生むのに役立つ1つの要因です。(“等像”レンズでは前と後ろの光学的部品を分離する空間は通常空気では満たされておらず、レンズの媒質自身で構成されています。)
“等像”レンズによって得られる拡大の供給に役立つ第2の要因は、レンズの“形”を変えて変化させられる前面と後面屈折力から生じます。ゆえに、“矯正”のジオプター度数が必要でない時でさえ、単純な“サイズレンズ”が作られる可能性があります。そのようなレンズの1つが下に図示されています。
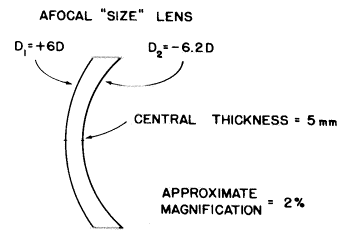
そのようなレンズに許される拡大の範囲をあなたに分かってもらうために、私は下のような小さな表を作りました。この表からあなたは5mmの厚さと+6Dの前面屈折力(後面屈折力は無焦点レンズとなるために約−6.2Dでなくてはなりません)があるレンズで約2%の拡大を生じることを決定できます。
表4
倍率(%)
|
レンズ厚(mm) |
D1(前面カーブのジオプター度数) +3D
+6D
+9D |
|
1 3 5 |
0.20
0.40
0.60 0.60
1.20
1.80 1.00
2.01
3.00 |
(数学に関心がある人だけのために― M(%)=D1×![]()
D1=前面屈折力のジオプター度数
t=厚さ(cm)
n=ガラスの屈折率)
この表はレンズの形(前面の勾配に支配される)とその厚さはちょうどレンズと目の間の頂間距離のようにその倍率に影響することを示しています。しかし、頂間距離のほうが日々の眼光学ではより重要です。形と厚さの効果は、私はもうこれ以上詳しく説明しようとは思いませんが、単純に“厚いレンズ”の光学の現れです。
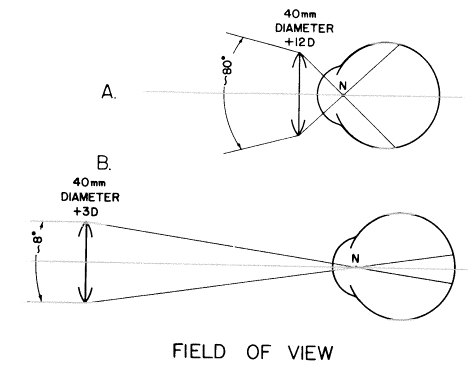
私たちはすでに無水晶体患者が彼の角膜から約25cmに置かれた+3Dのレンズで得られる4倍の拡大について言及しました。しかし、彼はこの“矯正レンズ”でその拡大を得るために何かをあきらめなくてはならず、その何かとは“視野”です。
上図から分かるように、矯正レンズが眼鏡レンズ面にある時、視野(レンズを通して見ることができる空間の範囲)はレンズがより遠い距離に置かれた時よりも広くなります。最初の例では視野は80゜ですが、その一方で倍率が4倍になると視野は約8゚に縮みます。
レンズの“中和”とガリレイ式光学の学習は、近視と遠視矯正で起こる網膜像の大きさの変化の考慮へと私たちを導きました。眼鏡レンズ面に置かれたレンズで乱視矯正をすると同様な問題が起きます。ここでの頂間距離の存在もまた拡大や縮小を起こします。問題はこの大きさの変化が等しくないことです―主経線に存在している両極端な大きさで起こる、経線による差動的な拡大が存在するのです。
よりプラスになった矯正レンズ度数を伴う経線はそれより小さい度数の経線より大きな倍率になります。これを視覚化するためには、プラス矯正レンズとマイナスになった目の“屈折異常”で構成されたガリレイシステムの断面図を思い出してください。その断面は最大のプラス度数のレンズ経線であり、それは最大のマイナスの屈折異常にもなっていなければならないとしましょう。この配列で、同じ目にあるどの他の経線よりも大きくなければならない、拡大された網膜像がこの経線上に生じることが分かるはずです。だから、もし垂直経線での矯正レンズ度数が他のどのレンズ経線よりもたまたま大きかったら、患者には垂直に伸びた像が見えるでしょう。
もう1つの例として、plano+4×90の矯正レンズを取り上げましょう。ここでは矯正プラス度数の最高値は180°の経線上にあります。ゆえに、像の水平の大きさは伸ばされるでしょう。もし物体が正方形ならば網膜像は水平な長方形のように見えるでしょう。
ここではこれ以上説明しませんが、あなた自身でそれを証明できます。乱視眼の“屈折異常”をシミュレーションするために−5×90の円柱レンズをあなたの目に近付けてください。“頂間距離”約5cmに+4.00×90を置いてこの屈折異常を“矯正”します。どんな物体(正方形と仮定します)でも水平方向の大きさが伸びるのが分かるでしょう。“矯正”レンズの置かれた距離を大きくすれば水平方向の倍率も大きくなります。
主経線が90°と180°の時はいつでも、それに対応する屈折力によって直線で囲まれた正方形の物体は横か上下に伸びるように見えるかもしれません。しかし、このタイプの見かけ上の歪みは通常患者にはあまりやっかいなことにはなりません。たとえ矯正レンズの軸が傾いていても(それで直角の角がいくらか鋭角か鈍角に見えるようになるかもしれません)、患者は数日か数週間の短い適応期間で慣れてしまいます。
臨床上の注意点:
しかしながら、主経線が傾いていて、そして両眼で違っていて、それゆえそれぞれの目の像線に違った“傾き”を与える時に問題が起こるかもしれません。これは複視を防ぐために回旋融像的眼球運動を必要とします。円柱度数をいくらか緩めに矯正することでこの“傾いた”タイプの歪みを減らす手助けになります。この技術はたぶん水平か垂直の方に矯正の軸を回転することで歪みを“直す”という試み(普通の方法)よりもいいでしょう。というのは後者の方法は、私たちが今までに見たように合成円柱屈折異常だけでなく球面屈折異常も加える傾向があるからです。(あなたがお互いに軸外になった異符号の円柱を結合した時何が起こるか思い出せますか?)しかし、両方の方法とも役に立ちます。